
2026年(令和8年)は午(うま)年です。
「午(うま)」は十二支の7番目にあたり、古来より俊敏さ・勇気・行動力の象徴とされてきました。
馬は、洋の東西を問わず人々の暮らしを支えてきた重要大切な家畜であり、特に移動や農耕で、戦(いくさ)にも欠かせない存在でした。
現代でも、競馬や乗馬などを通じて、私たちにとって最も身近な動物のひとつとなっています。
2026年は「丙午(ひのえうま)」!丙午生まれは強い?怖い?その本当の意味とは
 2026年は十二支十干(じゅうにしじっかん)で言えば「丙午」(ひのえうま)という組み合わせの年に当たります。
2026年は十二支十干(じゅうにしじっかん)で言えば「丙午」(ひのえうま)という組み合わせの年に当たります。
十二支十干は一般的にあまり知られていませんが、「丙午」(ひのえうま)だけはご存知の方も多いのではないでしょうか?
「丙(ひのえ)」は強い火を表し、「午(うま)」もまた火の性質を持ちます。
このため、火+火で「火の気が非常に強い年」とされています。
「丙午に生まれた女性は気性が荒く、夫を焼き殺す」という迷信が流布し、前回の丙午(1966年/昭和41年)には顕著に出生率が低下しました。
 しかし、本当に「丙午の女性」の女性は不吉なのでしょうか?
しかし、本当に「丙午の女性」の女性は不吉なのでしょうか?
火の気質は、燃えさかるような情熱・行動力・カリスマ性を意味します。現代において、それはむしろ「強み」と言えるでしょう。
2025年に日本で初めて女性の総理大臣が誕生しました。高い支持を得て、今後の活躍が期待されています。
この機運に乗じて丙午に突入する2026年は、社会のあらゆる分野で女性のリーダーシップが注目される年になるかもしれません。
「午」という漢字の由来と意味
「午」という文字は、餅をつくときに使う杵(きね)の形から生まれた象形文字です。
縦棒は杵の頭(つち部分)を、横棒は柄(え)を表しており、交差した姿が文字の形になりました。
つまり、「午」は穀物を搗(つ)く杵をかたどった文字なのです。
古代中国では、杵や臼は農耕や豊穣の象徴とされていました。
そのため、「午」はやがて農作業の盛んな時期や、「太陽が最も高く昇る時刻(正午)」を示すようになったと考えられています。
意味の変遷 ― 干支の「午」へ
のちに、「午」は十二支の一つとして使われるようになり、「午=馬(うま)」があてられました。
十二支はもともと、時間や方角、年を表すための記号であり、覚えやすくするために動物が対応づけられたものです。
「午」の時刻は午前11時から午後1時の間、方角では南を指します。
一日のうちで太陽が真南に昇り、陽の力が最も盛んになる時間帯です。
そこから、「午」は命の成熟や活動の最高潮を象徴する干支として受け継がれてきました。
「午」の文字デザインの年賀状テンプレート
午年生まれの人の特徴
「午(うま)」は太陽が最も高く昇る時刻を表す文字であり、活力・情熱・行動力の象徴とされています。
そのため、午年生まれの人もまた、明るく前向きでエネルギッシュな気質を持つと言われます。
午年生まれの人は、明るく社交的で、どんな場所でも自然と人を惹きつける魅力を持っています。
人懐っこく話し上手で、初対面の相手ともすぐに打ち解けられるため、周囲からは「ムードメーカー」として慕われることが多いでしょう。常に前向きなエネルギーにあふれ、何事にも積極的に取り組む姿勢が印象的です。
また、午年生まれの人は非常に行動力があり、思い立ったらすぐに行動に移すタイプです。じっとしているよりも、動きながら考えることを好みます。
直感的でスピーディーな判断が得意な反面、慎重さに欠けるところもあり、勢いで突き進んでしまうこともあるでしょう。
自立心が強く、他人に頼るよりも自分の力で道を切り開こうとする傾向もあります。そのため、仕事や人生においてリーダーシップを発揮することが多く、自然と人を導く立場に立つことも少なくありません。
また、競争心が強く負けず嫌いで、目標を決めたら最後までやり遂げようとする努力家でもあります。
一方で、感情表現が豊かで情熱的なぶん分、時には感情に流されやすくなることもあります。
思ったことを率直に口にしてしまい、人間関係で衝突が起こることもあるかもしれません。
とはいえ、基本的には裏表のない性格で、誠実さと明るさで人に愛される存在です。
総じて、午年生まれの人は太陽のように明るく、周囲に活力を与える存在です。
行動力と情熱をバランスよく活かすことで、どんな分野でも輝くことができるでしょう。
午年と相性の良い干支・悪い干支
午年と相性が良いのは寅年、戌年です。
寅年は午年と「三合(さんごう)」の関係にあり、非常に相性が良いです。お互いを刺激し合い、支え合える理想的な関係です。恋愛でも仕事でも良いパートナーになりやすいです。
戌年も午年と「三合」の関係です。どちらも誠実で情に厚く、信頼を大切にするため、長く安定した関係を築けます。
一方で、午年生まれの人と相性が悪いのは巳年、未年です。
巳年は午年と表面上は似ているようでいて、実は考え方が異なります。巳年の人は慎重でじっくり考えるタイプ、午年の人は直感で動くタイプ。そのため、テンポの違いから衝突しやすくなります。
午と未は隣り合う干支で、一見近いように思えますが、実は考え方や行動の方向性がズレやすい組み合わせです。お互いにペースを合わせる努力が必要です。
馬にまつわる神社
藤森神社
 藤森神社は京都市にある神社で、菖蒲(あやめ)の節句発祥の地として知られています。
藤森神社は京都市にある神社で、菖蒲(あやめ)の節句発祥の地として知られています。
「菖蒲」は「勝負」に通じることから、勝ち運のご利益があるといわれています。
創建は今から約1800年前、神功皇后によって建立されたと伝えられており、皇室ともゆかりの深い神社です。
 境内には神馬(しんめ)の像が設置されており、勝ち運のご利益と相まって競馬ファンの参拝者が多く訪れます。
境内には神馬(しんめ)の像が設置されており、勝ち運のご利益と相まって競馬ファンの参拝者が多く訪れます。
また、「勝馬守」や「うまくいく守」といった、馬にちなんだお守りも人気です。
 手水舎(ちょうずや)にも馬が登場します。
手水舎(ちょうずや)にも馬が登場します。
多くの神社では龍の口から水が流れ出ますが、藤森神社では馬の口から水が出る、珍しい造りとなっています。
⇒藤森神社 公式ホームページ
千束八幡神社
 千束八幡神社は東京都大田区、洗足池(せんぞくいけ)のほとりにある神社です。
千束八幡神社は東京都大田区、洗足池(せんぞくいけ)のほとりにある神社です。
「洗足池八幡宮」とも呼ばれ、品陀和気命(ほんだわけのみこと/応神天皇)を御祭神としています。
源義家が戦勝祈願を行った神社としても知られています。
 境内近くの洗足池には、「池月(いけづき)」という馬の銅像があります。
境内近くの洗足池には、「池月(いけづき)」という馬の銅像があります。
1180年、源頼朝が池のほとりに宿営した際に現れた野馬が、青い毛並みに白い斑点を浮かべ、まるで池に映る月のようだったことから「池月」と名付けられたと伝えられます。
また、頼朝がこの池で足を洗ったことにちなみ、池は「洗足池」と呼ばれるようになりました。
周辺には勝海舟夫妻の墓所や弁財天社などの史跡もあり、歴史散策の名所としても人気です。
⇒東京都神社庁 洗足八幡神社
上賀茂神社
 上賀茂神社は京都市にある神社で、境内全体がユネスコ世界文化遺産に登録されています。
上賀茂神社は京都市にある神社で、境内全体がユネスコ世界文化遺産に登録されています。
 神社では「賀茂競馬(かもくらべうま)」と呼ばれる伝統行事が行われ、実際に馬が境内を駆け抜けます。
神社では「賀茂競馬(かもくらべうま)」と呼ばれる伝統行事が行われ、実際に馬が境内を駆け抜けます。
競馬の起源には諸説ありますが、日本の競馬の源流の一つとされています。
ただし現在のような勝負事としての競馬ではなく、天下泰平と五穀豊穣を祈る神事として執り行われています。
⇒上賀茂神社
鶴岡八幡宮
 鶴岡八幡宮は神奈川県鎌倉市にある神社で、応神天皇を主祭神としています。
鶴岡八幡宮は神奈川県鎌倉市にある神社で、応神天皇を主祭神としています。
毎年9月16日の例大祭最終日には、流鏑馬(やぶさめ)神事が奉納されます。
この流鏑馬は、源頼朝が鎌倉幕府を開いた際、武士の統率と弓馬の鍛錬を目的に始めたと伝えられています。
頼朝は、武士たちに弓馬の技を磨かせるとともに、天下泰平と五穀豊穣を祈願しました。
その伝統は現代まで受け継がれ、鶴岡八幡宮の例大祭に欠かせない儀式となっています。
⇒鶴岡八幡宮
参考
- 生まれ年で人の9割がわかる!干支で見る性格診断|杉原理
- 「午」という漢字の意味・成り立ち・読み方・画数・部首を学習
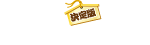
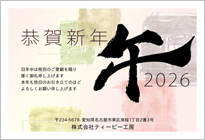





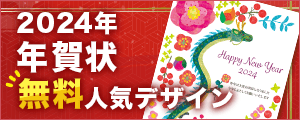





 TOP
TOP